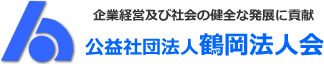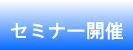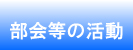2025年04月01日号
4月、値上げラッシュで家計を圧迫
4月、食品・日用品やサービス、電気・ガス料金、大学授業料、そして春闘での賃上げによる価格転嫁で広範囲での値上げが行なわれ、まさに家計に重くのしかかる新年度となる。帝国データバンクの調べによると、食品や飲料の4月の値上げは4170品目に及び、前年同月比1千目を超える広範囲な分野で行われる。電気・ガスも政府の補助金が終わり、NTT東日本のインターネット通信「フレッツ光ネクスト」の一部も利用料金が引き上げられる。
2023年児童虐待、最多の22万件超
厚生労働省とこども家庭庁のまとめによると、2023年度の虐待相談対応件数は過去最多の22万5509件に上ることが分かった。33年連続で増加してきている。約6割近くが暴言などで心を傷つける心理的虐待で、このうち半数を超えるケースは子どもの前で家族に暴力を振るう「面前DV」だった。虐待された子の年齢は3歳が約1万5千件弱で最も多かった。こども政策担当相は「核家族化や地域関係の希薄化で子育ての困難に向き合わざるを得ない家庭が多い」と指摘している。
WHO、米脱退で予算5分の1削減へ
世界保健機構(WHO)は予算の5分の1を削減する方針を示した。WHOは米国の脱退に加え、幾つかの国での防衛費増額により政府開発援助が削減されたことから2026~27年度予算案を53億ドル(約8千億円)から42億ドル(約6300億円)に削減したことを加盟国に提示している。テドロス事務局長は「世界の保健衛生を取り巻く状況はさらに悪化している」としたうえで、職員に活動縮小や人員削減が必要になると訴えている。
30年間で日本の平均寿命、5.8年延びる
慶応大チームの分析結果によると、日本の平均寿命は1990年~2021年の約30年間で5.8年延びて85.2歳となったことが分かった。また、47都道府県での最長と最短の差が1990年には2.3年だったが、2021年には2.9年に広がっていた。さらに、健康寿命と平均寿命との差は、1990年には9.9年だったが、2021年には11.3年だった。チームの野村慶応大特任教授は「健康な長寿の実現が課題だ」と指摘している。
コメ価格、11週連続値上がりの4172円
農林水産省の発表によると、3月10~16日に全国のスーパーで販売された米岐路足りの平均価格は4172円だったことが分かった。前年同期の2倍を超え、11週連続での値上がりとなっており、最高値を更新している。政府備蓄米の放出による値下げ効果はみられていない状況にあり、専門家は放出米が市場に出回っても値下がり幅は「数百円程度」との見方が出ており、前年同期の2千円台への回復は厳しいとみている。石破首相は備蓄米の追加放出も辞さない考えを示している。
科学者に対する信頼度、日本は59位
国際研究チームが新型コロナウイルス感染拡大後の2022~23年に68の国・地域に住む人を対象に科学者に対する信頼度を調べたところ、最高を5としたスコアが3.62だったと英科学誌に発表した。同チームは「ほとんどの国で科学者は信頼されている」と評価したが、日本は平均を下回る3.37で68の国・地域で59位だった。日本から参加した田中・早稲田大教授は「ワクチン接種や気候変動の問題で社会に分断が起きており、対話で解決するには科学への信頼が重要になる」と指摘している。
2023年時点での耐震化率は90%
国土交通省のまとめによると、全国で耐震性が確保されている住宅の割合は2023年時点で90%との推計だったことか明らかになった。同省では改修のほか、古い住宅の建て替え、解体で耐震不足の建物が減ったとみている。残る10%にあたる570万戸は最大震度7を観測された能登地震や熊本地震と同程度に揺れで倒壊する危惧がある。なお、耐震化率の推計は人が住んでいる住宅が対象で、耐震性がないものの、空き家となった物件は除外されることから、空き家物件の増加が耐震化率上昇の一因とみられる。
2024年小中高生の自殺、過去最多に
厚生労働省の警察庁自殺統計に基づいたまとめによると、2024年の小中高生の自殺者確定数は過去最多の529人となったことが明らかになった。小中高生の自殺者は2022年以降500人超で推移しており、2024年は小学生が15人、中学生が163人、高校生が351人となっている。原因・動機は「学校問題」が最も多く、その中でも「学業不振」「学友との不和」が続いた。自殺者の全体では2万320人に上り、原因・動機は「健康問題」が最多で、「経済・生活問題」が続いた。